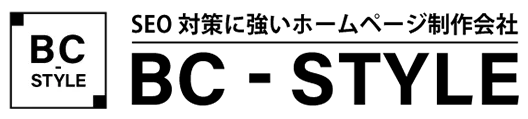ECサイトで売るコンテンツの作り方

独自ECサイトのコンテンツは
どのように作れば良い?(自社製品編)
今回は、独自ECサイトで、自社オリジナル製品を販売するにあたり、コンテンツ(内容)はどのように作れば良いかお話ししたいと思います。
テレワークを中心とした自宅でのお仕事が増加した影響で、ネット通販事業の売上が拡大しています。しかし、Amazonを初め、楽天やYahooショップなどの大手が大きく占めているのが現状です。その中で、自社独自のECサイトで売上拡大させるためには大手と同様なことを行なっていては勝てません。
そこで重要になってくるのがページコンテンツです。ページコンテンツを充実されることで、ターゲットユーザーに製品の魅力を伝えることはもちろん、販売価格以上の価値(付加価値)を付けることが可能になります。特にマイナーブランド製品を販売する際にはコンテンツは重要です。
1. 価値を考える
価値を考えるというのは、「製品」や「販売者」の価値です。
そこでお客様が販売者(独自ECサイト)から製品を購入した場合に、そのお客様はどのようなメリットを付与できるのか考えます。
例えば以下のように。(製品の性格により出せるメリットが違います)
- このような方にこの製品は満足してもらえる
- 他社の類似品より安価
- 他社では買えない
- 全額返金保証がある
- 注文してから製品が届くまで早い
- 購入後の製品サポート体制がある
- 定期購入の割引がある
- 製品に関連した情報が豊富にある
以上の1から8の例には、製品の価値と付加価値(製品に特別な価値を付与するもの)が混在していますので、これを分けます。
製品の価値
- このような方にこの製品は満足してもらえる
- 他社の類似品より安価
付加価値
- 他社では買えない
- 全額返金保証がある
- 注文してから製品が届くまで早い
- 購入後の製品サポート体制がある
- 定期購入の割引がある
- 製品に関連した情報が豊富にある
2. 価値・付加価値の内容を考える
製品の価値と付加価値に分けましたら、製品価値の内容をできるだけ多く箇条書きにします。
例)
製品の価値
- このような方にこの製品は満足してもらえる
製品の規格、説明、メリット、製品で解決できること、製品をお勧めしたい方、等々です。 - 他社の類似品より安価
他社の類似品と比較して、安価であることを具体的に書き出します
次に付加価値の内容を箇条書きにします。
例)
付加価値
- 他社では買えない
独自ECサイトのみで販売している理由を書き出します。例えば、「ご購入いただいたお客様へのサポート万全にするため」などです。 - 全額返金保証がある
具体的にどのような全額返金保証がどういう内容なのかを箇条書きにします。 - 購入後の製品サポート体制がある
購入後、製品の使い方や困りごと、質問等、購入後のサポートがどのようなものがあるのかを箇条書きします。 - 定期購入の割引がある
定期購入することによってどれだけ安くなるのかユーザーの頭の中でイメージできる内容にします。例えば、「定期購入すると、初回製品価格00割引き!」のような感じです。 - 製品に関連した情報が豊富にある
製品の有効利用の方法やワンポイントアドバイスなど、その製品の価値を高める情報を箇条書きします。
3. 価値・付加価値の文章を書く
製品の価値と付加価値の箇条書きが完成しましたら、各々その内容を文章にします。
文章の書き方のポイントはできるだけ詳しく書くことです。販売側は製品のことや会社のことは当然分かっているので、ターゲットユーザーが単純に疑問に思うことの説明などが抜けてしまうことが多いです。文章が完成したら、販売者や製品について知らない第三者に読んでもらい、こちらの伝えたいことが十分理解できるかどうか感想を聞くのが良いと思います。
4. 製品のストーリーを作る
製品のストーリーとは、例えば製品開発物語です。「毎日—に困っている妻を見て、それを解決するために開発した製品です。その製品を開発するために試行錯誤したことや苦労など。製品が完成した際、妻に使ってもらったら問題が解決できて物凄く喜んでくれた。」というようなストーリーを作ります。このストーリーを作ることによって、同じような問題を抱えているターゲットユーザーの心に訴求効果が得られます。
5. 販売者の思いをコンテンツにする
「販売者の思い」は、言い換えれば経営理念です。具体的に「経営者の思い」に、考え方や価値観を加えて文章にします。堅苦しく書く必要はありません。販売者の思う気持ちを率直に書くと良いでしょう。これを書くことにより販売者の信用度が上がります。
6. Q&Aのコンテンツを作る
ECサイトでよく目にするQ&Aですが、これを書くときに注意しないといけないことは、製品のメリットとなるQ&Aだけを書かないことです。
どのような製品にもメリットとデメリットがあります。質問事項でデメリットとなるものを避けて、回答がメリットばかりのQ&Aにしてしまうと逆に製品の信頼度が落ちます。
今回はここまでです。続きは近日中にアップします。